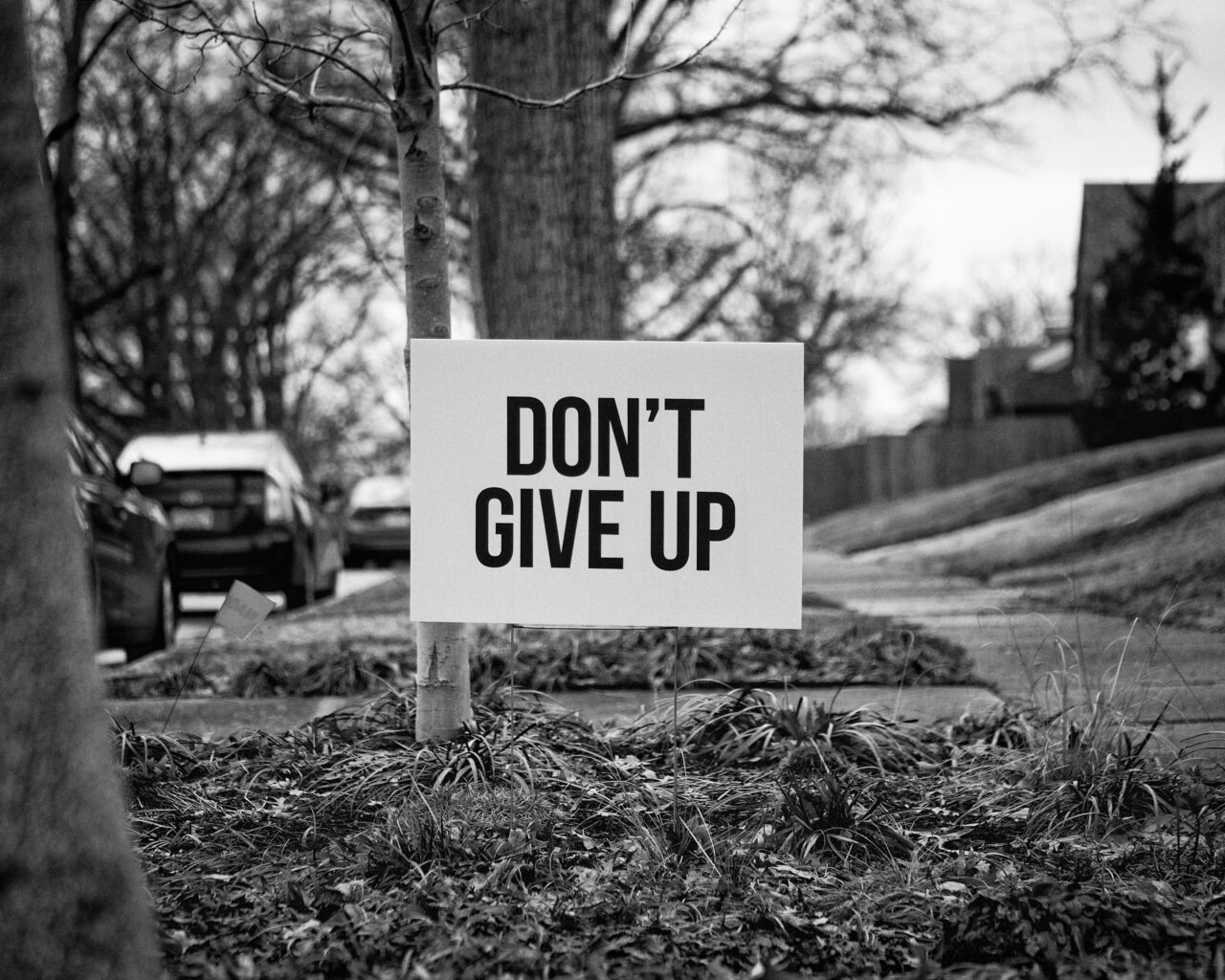就活の軸って何?どうやって考えたらいいの?
軸を持って就活に取り組んだ方がいいって聞くけど、どうやって作ればいいか分からないよ…。
就活の軸はなんとなく決まってきたけど、その軸と企業がどれだけ調和しているかが分からない…。
就活生は「就活の軸」を持って就活に取り組むのが一般的だよね。就活の軸をしっかり作れないまま就活をしていると自分の方向性を見失ってしまう可能性が高いから、冬に向けてしっかり自分と向き合っていこう。
この記事では、某大手企業に内定をした先輩の話をもとに、就活の軸の作り方について詳しく解説していくよ。「就活の軸が決まりきっていない」「自分の就活の軸はこれでいいのか不安」そんな就活生はぜひ読んでみてね!
1.就活の軸とは
就活の軸を作る目的
就活の軸を作っておく目的は、簡単に言うと「自身のスタンスを決め、選考に受かりやすくする」ことです。
就活の軸に沿ったESや面接での発言をすることによって一貫性のある発言ができるので選考に通りやすくなります。
また、企業を選ぶ際の判断材料とすることもできます。
それによって「納得就職に繋がる」というのが、就活の軸を作る大きなメリットです。
就活の軸はとりあえずでも持っておくほうが良い!
たとえ自己分析を十分に行えておらず洗練された就活の軸が定まっていない場合でも、仮でも良いので就活の軸を言えるようにしておきましょう。
暫定の就活の軸を決めておく理由は主に2つあります。
一つは、選考の際に求められるからです。ESや面接で就活の軸を聞かれたときに、「決まっていません」と言うのと「現時点では〇〇という軸を持っています」と言うのでは雲泥の差があります。
もう一つは、企業選びや自己分析で悩んだ際の着地点(セーブポイント)になるからです。
自己分析をしているときは特に、いろいろな要素を考えすぎて、自身の軸とはかけ離れたことを考えることもあるでしょう。そんなときに仮の就活の軸を持っておくことで「帰ってこられる場所」を担保できるわけです。ただし、仮の軸が自身の軸とかけはなれたものだと本末転倒なので、最低限自分が納得できる仮の就活の軸を置いておくことは重要です。
また、次章でも話しますが、他者との対話によって第三者から客観的な視点で就活の軸を考えてもらう際に、暫定の就活の軸があるとフィードバックをもらいやすい(与えやすい)というのもメリットの一つです。
2.就活の軸の作り方
就活の軸は一人では完成しない!?
就活の軸を作る際にいちばん大事な考え方は「一人でやろうとしない」ことです。
多くの就活生は、他の人の時間を取ってしまうのをためらってか、自分ひとりで就活の軸を作ろうとしてしまっています。
しかしながらそれでは納得の行く就活の軸は絶対に完成しません。
みなさんは「ジョハリの窓」を知っているでしょうか?
ジョハリの窓は「自分自身が見た自己と他者から見た自己をそれぞれ分析し、4つに区分することで自己を理解するもの」で、自己分析によく利用する心理学モデルです。
①自分が知っているかつ他人も知っている自分の性質(開放)
②自分が知らないかつ他人は知っている自分の性質(盲点)
③自分が知っているかつ他人は知らない自分の性質(秘密)
④自分が知らないかつ他人も知らない自分の性質(未知)

この図の考え方を備えることで、就活の軸づくりが一人では達成できないことがよく分かると思います。
特に「②盲点」の部分は他者と対話して初めて得られる自分の姿なので、積極的に他者に就活の軸作りを手伝ってもらい、自分の性質を洗い出してもらいましょう。
具体的な就活の軸の作り方
では具体的に、だれにどのようにして就活の軸作りを手伝ってもらえばよいのでしょうか?
これには大きく分けて4つの方法があります。
①就活サービスやOB訪問アプリを使って先輩就活生と面談を行う
他者を巻き込んだ就活の軸の作り方のもっとも基本的なものが、OBOGとの面談です。
就活に大成功した先輩が揃うキャリアエッセンスの「面談対応サービス」をはじめ、OBOG訪問アプリの「Matcher」などの利用がおすすめです。
最近ではオンラインが主流になっており、以前よりも気軽に多くの人と話せるようになりました。この機会を存分に利用して、信頼できるOBOGを見つけて就活の軸作りを手伝ってもらいましょう。
②就活の軸づくりに役立つ就活サービスを利用する
世の中には就活の軸作りに役立つサービスが数多く存在しています。
その中でもおすすめなのが「ジョブティ」です。
ジョブティは、実際に営業の業務を体験していただくことで、たったの90分であなたの実務上の実力を測ることができる画期的な就活サービスです。
あなたが今まで気づかなかった自身の強みを見つけるきっかけになると同時に、学歴だけでは測ることができない本当の仕事力を磨くことができます。
さらに、受検後には就活の先輩や社会人の方から直接フィードバックをもらうことができるので就活の軸作りに役立つこと間違いなしです。
会員登録はこちらから↓
https://app.careeressence.jp/mypage?resume=1628423443616×327243859873733950
③就活セミナーやイベント終了後に会場に残り、社会人の方とお話しする
就活の軸をブラッシュアップするために社会人の方と話す作戦として、セミナーやイベント終了後会場に残るというものがあります。
この作戦の大きな強みは、セミナーに登壇している実績ある社会人からの意見をもらえる、もしくは企業の採用担当の方と話す機会が得られることです。
場合によっては企業の社長に話を聞ける可能性もあるでしょう。
キャリアエッセンスでは、著名な登壇者も招いた毎月3〜5回のイベントが開催されています。
イベント終了後に登壇者や運営の内定者・社会人と話せる時間もあるので、「就活の軸を決めたい」「就活についてもっと知りたい」と感じる就活生にはとてもおすすめのサービスです。
④日々の事象に対する考え方や感想を友人とシェアする
先輩や社会人といった年上の人だけでなく、同年代の就活生から印象を聞いたり意見を交わしたりすることも就活の軸を決める手がかりになります。
企業に所属したら年上の先輩だけでなく、同期の社会人やいずれは後輩も持つことになるでしょう。そういう相手に対して与える印象というのは、今の同期や後輩に与えている印象と大差はないと思います。
そのため、就活の軸を作る際に同期や年下からの印象も聞いておくことで、より先を見据えた形の就活の軸を定めることができるでしょう。
おすすめしない就活の軸の作り方
今までおすすめの就活の軸の作り方を紹介してきましたが、おすすめしない就活の軸の作り方もあります。
それはずばり、「一問一答形式の質問に答えるだけ」の方法です。
書籍やネット、就活サービスの中には、質問に答えるだけで自分の性質が分かるというものがいくつもあります。
もちろん、それらを使うことが全く意味がないとは言いません。
しかしながら、その質問に答えるだけで満足してしまうと、本質的な「就活の軸」を定めるところから離れていってしまいます。
質問に答えて得られる性質は、あなたの軸の枝葉の部分でしかないのです。
ですので、一問一答形式の質問を通して、埋めるだけでなく深く考える使い方をするようにしましょう。
3.就活の軸と企業選びの照らし合わせ方
就活の軸が決まったら、次の段階として就活の軸に沿った企業選びや選考に挑むことになると思います。
ここで気をつけておくとよいのは、軸には階層があり、企業選びや選考の際には下層の就活の軸を特に意識することです。(上位層にキャリアや人生の軸)

企業選びや選考の際に軸の上位層のみを意識してしまうと、「なかなか軸に合う企業が見つからない分からない」「企業に貢献できることが示しづらく選考に不利になってしまう」可能性が高いです。
ですので、上位層の就活の軸を他者との会話でブラッシュアップしながら、企業選びや選考のための下位層の就活の軸も置いておくようにしましょう。
4.不安な人はキャリアエッセンスで面談を!
いかがだったでしょうか。
今回の記事では「就活の軸は一人だけでは作れない」というテーマで、就活の軸の作り方について紹介してきました。
とはいえ、ブログを読んだだけで悩みが解決することはないと思います。
この機会に先輩やOBOGとの面談の機会を自ら設け、就活の軸作りの一歩を踏み出してみて下さい。
↓
みなさんの就活の成功の一助になれば幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。